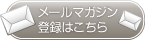TOPページ > パワーアップ会議から > トップインタビュー「私とメンター」
トップインタビュー「私とメンター」
Vol.8
(インタビュアー:アキレス美知子 ワーキングウーマン・パワーアップ会議 推進委員)
ダイバーシティを進めるとイノベーションは必ず起こる
斎藤 保 株式会社IHI 代表取締役社長 最高経営責任者
「ワーキングウーマン・パワーアップ会議」(事務局:日本生産性本部)では、女性の力を活かし、組織の生産性向上につなげる動きを加速させるため、女性と組織を応援しています。 第8回は、株式会社IHI 代表取締役社長 最高経営責任者 斎藤 保氏に、ご自身の経験から「メンター」と女性の活躍への期待について伺いました。(インタビュアー:アキレス美知子 ワーキングウーマン・パワーアップ会議 推進委員)
指導教官から「ものづくり」の会社でしっかり取り組むように勧めてもらった
アキレス日本でもこの4、5年、ようやくメンター・メンティという言葉を聞くようになりました。メンターという名前が付いていなくても、壁にぶつかったり悩んだときに、相談しに行ったり、アドバイスや示唆をいただいた方はいらっしゃいますか。
斎藤これまでの経験から、よきアドバイスをしてくれる人、いろいろな悩みについて聞いてくれる人というのが、私にとってのメンターかなという気がしています。自分の性格もあると思いますが、いろいろな人の影響を受けやすいので、時代時代で出会ったインパクトのある人たちが、みなさんメンターになってくれたと思います。
アキレス素晴らしいですね。中でも印象に残る方はいらっしゃいますか。
斎藤物心ついてという意味では、高校時代の歴史の先生がいらっしゃいます。かなりインパクトのある先生で、この方に「歴史とは何か」ということを学びました。それと、黒板にものすごく字を書くし、話も沢山する方なのですが、口述をすべて筆記しろと言うのですね。
アキレスそれは大変ですね。
 |
| 斎藤 保(さいとう たもつ) 東京大学工学部卒業後、石川島播磨重工業(現IHI)入社。2006年6月執行役員、2008年1月航空宇宙事業本部長、4月取締役、2009年4月常務執行役員、2011年4月代表取締役副社長を経て、2012年4月より現職。一般財団法人製造科学技術センター理事長。 |
大学では、航空工学を学んでいたのですが、卒業論文・卒業設計の指導教官がいらっしゃいました。当時は学問としてはあまりメジャーではなかった破壊力学をもう少しやってみたいと思っていた時に、「それをやるなら、いわゆるものをつくる会社でしっかりやるべきじゃないか」と言って、当時、航空エンジンでナンバーワンの会社だったIHIに入れと勧めてくれました。
航空学科の先生たちは個性的な人が多かったですが、この方は穏やかな先生でしたね。学問的な位置付けや論理的な発想をしっかりとされるし、ものづくりにかける思いがある方でした。製造業やものをつくるということに対する意識をしっかり教育してもらったという意味で、大きな影響がありました。
アキレス社会人になってからはいかがですか。
部下を育成したいと思う上司の気持ちに気づいた瞬間に相通じた
斎藤入社3年目ぐらいまでに出会った上司というのは影響がありますね。当時、特に航空宇宙事業本部は、個性がありすぎて変わっている人が多くて、厳しかった。われわれも怒られたり、相当激しく罵倒されたりしましたが、しばらくして気が付いたのは、根底には人材を育成したいという気持ちがあるということなのです。それが分かった瞬間に相通じたという感じがします。そういう話をしてくれることはあまりありませんでしたが、その人をどう育成していくか、何が向いているだろうかということを真剣に考えているのですね。それが飲み会の場などで、ぼそっと話が出てきたりすると、「ああ、よく考えてくれているんだな」と感じていました。アキレス日本企業の典型的なコミュニケーションですね。
斎藤そうだと思います。うちはもともと造船ですので、そのスタイルが強いようです。すり合わせ型の製品などもありますので、個別に上司がフォローする密なコミュニケーションを取っていることが多いですね。
アキレス今もそういう形で続いていらっしゃるのですか。
斎藤続いている面と、濃厚な接触があったわれわれから見ると、希薄化していると感じる部分と両方あります。その希薄化している部分をどう解消するか。連携を深めるには、話をしなければいけません。もう少し接触回数を増やすことを、会社の中でもやればいいのかなという気がします。
お客様のところでは、宿題を必ずもらうようアドバイスを受け、今でも実践
アキレスそういった密なコミュニケーションの中で、学ばれたことも多かったのではないでしょうか。斎藤学生から会社へ入って一番驚きだったのは、スピードが違うことでした。自分の上司の中でも、一番厳しい方だったのではないかと思うのですが、議事録を会議の終了直後に出せと言うのですよ。普通はメモを取って、後でまとめてから出すでしょう。ですから、会議をしながら議事録をまとめたり、出張報告は帰りの新幹線で書いたりしました。これにも高校の時の速記が役に立ちましたね。
また、これは今でも実践していますが、当時の上司が「お客様のところに行ったら宿題を必ずもらってこい」と言うのですね。お客様のところに説明に伺った時に、答えられないものについては、少し距離を置きたいから、一生懸命ガードしながら「それはできません」という話になるのですが、上司に「それでは駄目だ」と言われました。とにかく持ち帰って、「では、また来週来ます」と言ってこいと言うのです。後で考えてみると、それはお客様との接触回数をどう増やしていくか、お客様とコミュニケーションを取ることが大事だということなのですね。これは今の営業の現場にも伝えています。
アキレスただお客様へ行くというわけにはいきませんから、少しでも役に立つものをお返しするということですね。
斎藤接触回数が増えるほど、資料がブラッシュアップされて、自分の考えも整理されてよくなっていく。お客様とも親密になりますし。これは大変よいアドバイスだったと思っています。
もともと学生の時には、設計や開発、研究をやりたかったのですが、配属されたのは、いきなり現場、工場でした。当初は「何で」という感じがありましたが、入ってみると面白かったですね。私は常々、三現主義「現場、現物、現実」を言っているのですが、その根底になっている「ちゃんとものを見て、ちゃんと現場に行って判断しろ」というところを叩き込まれたのがよかったですね。