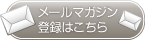TOPページ > エンパワーメント・フォーラム2012 > 開催レポート
開催レポート
「エンパワーメント・フォーラム2012」開催レポート
 日本生産性本部と働く女性のパワーアップを応援する運動を展開している「ワーキングウーマン・パワーアップ会議」は、2012年2月24日(金)に、「エンパワーメント・フォーラム2012」を女性就業支援センター(東京・港区)で開催し、多数の参加者のもと、基調講演および「メンタ―・アワード2012」の表彰式や、受賞組織による事例紹介を行った。
日本生産性本部と働く女性のパワーアップを応援する運動を展開している「ワーキングウーマン・パワーアップ会議」は、2012年2月24日(金)に、「エンパワーメント・フォーラム2012」を女性就業支援センター(東京・港区)で開催し、多数の参加者のもと、基調講演および「メンタ―・アワード2012」の表彰式や、受賞組織による事例紹介を行った。
冒頭、ワーキングウーマン・パワーアップ会議顧問 牛尾治朗日本生産性本部会長は、「景気の低迷や少子高齢化といった課題に対して、社会の基本的な構造を考えなくてはいけない。潜在力が強いのは女性である。WWPは女性の地位を上げようと始めたが、性差の壁を超えて能力を発揮しないと経済が成り立たない時代になってきた。これからいよいよ本格的に、女性が経済を担い、明日を創造する力が求められている。」とし、「グローバル化、IT化によって、女性が強みを発揮しやすくなっている。日本が世界の経済の中で大きな力を持つためにも、女性の力を還元できるようにしていかなくてはならない。新たな日本経済を担う仕組みをどうしていくかを議論していかなくてはならない。」と述べた。
また、「女性をいち早く開花させようと努力する企業は人柄がよい企業が多い。私がお会いする企業のトップやメンタ―もチャーミングな人が多い。世界から日本人の人柄の良さ、丁寧さが高く評価されている。今日の受賞者は胸を張ってもらいたい。」と受賞者へ声をかけた。
基調講演「自信のなさは努力で埋められます!」
 基調講演には、同会議代表幹事 橘・フクシマ・咲江氏(G&S Global Advisors Inc. 代表取締役社長)が「自信のなさは努力で埋められます!」のテーマで登壇した。フクシマ氏は、「今、日本は女性のグローバルな活躍を必要としている。ぜひ自信をもってグローバルなキャリアを目指してもらいたい。そうでなければ日本はこのまま縮小をしてしまうのではないかという危機感を持っている。」と訴えた。
基調講演には、同会議代表幹事 橘・フクシマ・咲江氏(G&S Global Advisors Inc. 代表取締役社長)が「自信のなさは努力で埋められます!」のテーマで登壇した。フクシマ氏は、「今、日本は女性のグローバルな活躍を必要としている。ぜひ自信をもってグローバルなキャリアを目指してもらいたい。そうでなければ日本はこのまま縮小をしてしまうのではないかという危機感を持っている。」と訴えた。
氏が仕事をする上でのこだわりに、ダイバーシティの考え方がある。「国籍等でその人を決めつけず、一人ひとりの個人を見ることが、これからのグローバル化の中では必要であり、国籍、人種、宗教、年齢等々は、その人の一個性に過ぎない。日本の経済再生には女性の力が不可欠で、女性の労働力をアメリカ並みに高めれば0.3%経済は成長し、個人の所得も1.5%増加すると言われている。カタリストの調査では、女性役員の多い会社上位4分の一と下位4分の一を比較した結果、業績の向上に差があったというデータもある。世界は急速にグローバル化しており、グローバルなチェンジエイジェント人財(市場価値のある)が求められているのに、日本ではドメスティックな管理者的人材が多いという需要と供給のミスマッチが生じていた。日本企業は、グローバル競争力が低下している上にグローバル人財も不足している。女性はグローバルリーダーとしての素質があるのでぜひ活躍して欲しい。」と述べ、好きな言葉である「外柔内剛(自分の日本人としての信念は譲らず外には多様性に応じて柔軟にしたたかに対応する)」を会場の女性に贈った。
第4回「メンター・アワード2012」表彰式開催
 続いて行われた、「メンター・アワード2012」表彰式では、第一生命保険株式会社、株式会社髙島屋、国立大学法人名古屋大学の3組織がメンター制度表彰優秀賞を受賞するほか、メンティからの応募に基づき選考されたメンター個人表彰も行われた。
続いて行われた、「メンター・アワード2012」表彰式では、第一生命保険株式会社、株式会社髙島屋、国立大学法人名古屋大学の3組織がメンター制度表彰優秀賞を受賞するほか、メンティからの応募に基づき選考されたメンター個人表彰も行われた。
表彰式では、同会議推進委員の田村洋一郎氏(㈱日立製作所)が、以下のように講評を行った。
○第一生命保険 各所属の女性職員のうち、管理職候補者を「ダイバーシティ推進者」と任命し、当該所属の他の女性職員の意識改革・行動改革の牽引役として、次のステップに向けた意識付けや、業務内外の悩みなどの相談、アドバイスを実施している。 さらに、このダイバーシティ推進者にも、上位メンターとして、所属を越えた女性管理職が「ブロックリーダー」となり、キャリアアップのための相談に乗っており、全国の女性職員をカバーする「メンターネットワーク」が構築されている。 このように、女性社員一人ひとりと丁寧な対話を行ってきた成果として、女性管理職は継続的に増えるほか、上位職位に前向きな女性職員の割合も大幅に増加している。
○髙島屋 入社から専門能力の発揮段階までの10年間を若手人材の育成期間と設定・明確化し、育成策の一環として、メンター制度を実施。メンティは、主任に進級の翌年、入社4年目の社員、メンターは、入社10年目前後の課長の組み合わせとなっており、メンターの経験談や助言を通して、自律した自己成長を促している。 また、円滑に制度を運用していくため、制度や期待役割に対する理解を深めるための事前ガイダンスの実施や、メンターへ、メンタリングスキルを向上させるための研修を実施し、中長期的な視点でキャリアを考えられるようになった、職制以外に社内ネットワークが広がったなどの声も多くでてきており、女性管理職の一定割合の輩出にも繋がった。
○名古屋大学 入職後3年目までの教員に対して、中堅教員がメンターとなる「教員メンタープログラム」を2005年から実施している。メンター、及び、メンティのためのガイドをそれぞれ作成することで、メンターとメンティによる主体的なメンタリングの実施を効果的に支援した。これまで継続してきたことで、学内で、メンタリング・プログラムの意義が着実に浸透し、プログラム利用者は年々増加しており、教育や研究を進める上でアドバイスを得られたなどの成果も見られている。 また、女性教員の数も、着実に増えきている。
 事例紹介では、同会議推進委員の前畠孝子氏(㈱りそなホールディングス)の進行により、第一生命保険㈱ 人事部 ダイバーシティ推進室 部長 吉田久子氏、㈱髙島屋 企画本部付 課長 山本倫代氏が発表した。
事例紹介では、同会議推進委員の前畠孝子氏(㈱りそなホールディングス)の進行により、第一生命保険㈱ 人事部 ダイバーシティ推進室 部長 吉田久子氏、㈱髙島屋 企画本部付 課長 山本倫代氏が発表した。
プログラム終了後には、推進委員、メンター・アワード受賞者と参加者による交流会を開催し、活発なネットワーク作りが行われた。
(文責:事務局 企業名・役職名は開催当時のものです。)